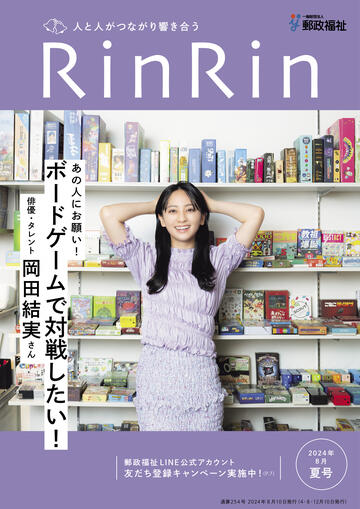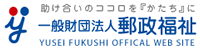 総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月
総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月

- ページ: 13
- 1・
いくらかかる? 死後のお金。
受け取れるお金とともに確認
人生最期のとき。遺された人の負担をなるべく減らす
ためには、どのような備えが必要なのでしょうか。
3・
家族のために今から準備。
保険でできる死後の備え
財産の遺し方も工夫しましょう。死亡保険金には次の
3つのメリットがあります。
遺された人が払うお金。
相続税の基本をおさらい!
相続財産は、遺言があれば基本的にそれに従い、遺言
がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行って相続
2・
割合を決めます。遺産の分け方が決まったら、相続があ
1つ目は、死亡保険金の節税効果です。死亡保険金に
は遺族の生活費という目的があるため、「500万円×
カ月以内に相続税の
最 期 に は、 病 院 へ の 支 払 い や 遺 族 の 当 面 の 生 活 費 な ど、
・8%にとどまります。ただし、このほかにも人生の
葬 や 納 骨 堂 を 選 ぶ 人 が 増 え た た め、 一 般 墓 の 購 入 者 は
なお墓の平均額は149・5万円ですが、最近では樹木
よりも費用は低下傾向にあるといいます。また、一般的
800万円までの遺産には相続税がかかりません。
相 続 人 が 妻 と 子 ど も 2 名 の 合 計 3 名 の 場 合 は、 4 千
「3千万円+600万円×法定相続人数」。例えば、法定
ただし、相続税は相続財産から基礎控除を差し引いた
残 り が 相 続 税 の 対 象 に な り ま す。 基 礎 控 除 の 計 算 式 は
申告を行い、相続税を納める決まりです。
2つ目は、相続税の納税資金の確保です。相続税の納
税 期 限 は カ 月 で す。 相 続 財 産 が 不 動 産 の み だ と 納 税
けば、相続税の課税対象を3千700万円に減らせます。
険金の非課税金額としてさらに1千500万円を差し引
礎控除を差し引くと5千200万円となります。死亡保
続財産を3名の法定相続人が相続した場合 、1億円から基
法定相続人数」が非課税になります。例えば、法定相続人
ったことを知った日の翌日から
まとまったお金が必要になります。
仮に相続財産が1億円の場合、基礎控除を差し引いた
5千200万円が課税遺産総額です。これを法定相続分
死後にかかるお金のうち、葬儀費用は110・7万円
(左図参照)ほど。小規模な葬儀や家族葬が増え、従来
葬儀や埋葬に対する公的な給付としては、国民健康保
険の「葬祭費」
、健康保険の「埋葬料(埋葬費)
」があり
( 妻 2 分 の 1、 子 4 分 の 1 × 2 名 ) で 案 分 す る と、 妻
が3名なら1千500万円が非課税に。仮に1億円の相
ますが、支給額は平均して5万円前後が相場といわれて
10
います(自治体や加入する組合による)
。このため、自
妻 3 4 0 万 円、 子 1 4 5 万 円 × 2 名 で、 合 計 6 3
2千600万円、子1千300万円×2名。相続税額は、
が納められるというわけです。
険金を用意しておけば、不動産を処分しなくても相続税
資金確保に苦労しますが、あらかじめ生命保険で死亡保
分で万が一に備える必要がありますが、亡くなった人の
額を相続割合に合わせ
いろいろあります。口座凍結でお金が引き出せなくても、
0万円です。実際の相続割合が異なる場合は、この合計
が 終 わ る ま で 凍 結 さ れ、
て 再 配 分 し て、 各 自 が
死亡保険金はすぐに受取人宛てに振り込まれます。
金 融 機 関 口 座 は、 相 続
入出金などができなく
納税します。
3つ目は、すぐに使いたい現金の用意です。葬儀費用、
お墓の購入、遺族の生活資金など、死後に必要な出費は
な り ま す。 仮 払 い 制 度
も あ り ま す が、 相 続 人
1人が仮払いできるの
は1金融機関で150
万 円( た だ し、 口 座 残
高×3分の1×仮払い
を希望する人の法定相
続 分 ま で ) が 上 限。 貯
め る だ け で な く、 お 金
の引き出しやすさも考
えておきましょう。
13
10
21
出典:株式会社鎌倉新書「いいお墓」より「第15 回 お墓の消費者全国実態調査」
�
- ▲TOP
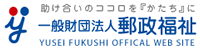 総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月
総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月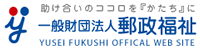 総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月
総合情報誌RinRin Vol.254[夏号] 2024年8月